風に舞うタネたち(2020.11.11)

立冬を過ぎて暦の上では冬ですが、これから秋がグッと深まっていきます。春から夏にかけて、 花を咲かせ実をつけてきた植物たちですが、秋が深まってくると子孫を残すために種子を拡げる という大事な仕事が残っています。自分では動けない(動かない)植物たちは、動物に付着するな どいろいろな周りのものを利用して種子を拡げます。そのひとつが「風」の利用。 カエデ科の仲間は、種子を包む子房が翼のようになって風を受けます。この翼は、子房が変化 した果実なので翼果(よくか)と呼ばれ、プロペラ状になって風に舞って落下していきます。 最初に紹介したのはイタヤカエデ【板屋楓】。現在園内では、紅葉前のいろいろなカエデ科樹木 に付いている翼果をいろいろ観察することができます。
 イロハモミジ
イロハモミジ
植物たちは、翼果以外にもいろいろな部位で風を受けて、種子を拡げます。 アオギリ【青桐】(アオギリ科)は、果実の皮が5つに分かれて開き、舟形の裂片に種子を付けて 風に舞います。
セイヨウシナノキ【西洋科木】(シナノキ科)は長い果柄の先に果実を付けますが、成熟すると基 部にある苞葉とともに枝から離れて風に舞います。
クマシデ【熊四手】(カバノキ科)は、種子を抱いた果苞が房状(果穂)になって下がりますが、果 穂が熟すと種子は果苞に包まれたままバラバラになって風に舞います。
ユリノキ【百合木】(モクレン科)の果実は翼果がたくさん集まった集合果ですが、これも熟すとバ ラバラになって風に舞います。
その他、熟して茶色くなってもいつまでも枝に残るネムノキ【合歓木】(マメ科)の鞘や、果皮が風 船状になるモクゲンジ【木患子】(ムクロジ科)なども、風を受けて種子の散布範囲を拡げるための 形のひとつといえるのではないでしょうか。
園内で風に舞う種子を見つけて、深まる秋を感じてください。 (解説員)











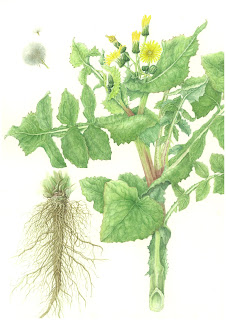
コメント
コメントを投稿