独特な形の雄花と雌花~ソテツ(2020.8.8)
暦の上では立秋を過ぎましたが、連日うだるような暑さが続いています。園内の植物は全体的にバテ気味の様子ですが、暑さにもめげず濃い緑色の羽状葉をびっしりと繁らせて、たくましい存在感を示しているのが温室前のソテツ【蘇鉄】です。九州から南西諸島にかけて自生が見られ、幹の先端部分に葉を広げる特徴的な姿は、暑い南国の雰囲気を感じさせます。
 |
| 雄花 |
ソテツは、イチョウやマツなどと同じ「裸子植物」です。裸子植物とは、胚珠(はいしゅ;成長して種子になる)がむき出しになっているもので、現在生きている植物の中では、イチョウと並んで最も原始的なものの一つとされています。雌雄異株で、幹の頂部に独特な雄花・雌花をつけます。
温室前では通路を挟んで左右に植栽されており、温室に向かって左側が雄株、右側が雌株です。 |
| 雌花 |
雄花は、円柱状で表面は鱗(うろこ)で覆われたようになります。その形は「松ぼっくりを長く引き伸ばしたようなもの」とよく説明されますが、雄花が出てきて間もない姿を見てみると、その意味がよくわかります。
 |
| 7月初めの雄花 |
雌花は、幹の頂部に折り重なってドーム状に膨らんだ形になりますが、秋には種子が成熟してオレンジに色づきます。
 |
| オレンジ色の種子 |
この種子は有毒ですが、澱粉質も多く十分な処理をすれば食用になるので、かつて南西諸島などでは飢饉の際の救荒食物とされたとの伝承があります。
学名は「Cycas revolute」で、属名シカスは「ヤシに似た植物」、種小名リヴォルタは「反巻した」という意味から付けられており、種小名は出たばかりの若い葉を見ると、その意味がよくわかります。
ちなみに和名の「蘇鉄」の由来とは、枯れかかった時に幹に鉄クギを打ち込むと元気によみがえるとの伝承によるといわれています。
ソテツを観察する時には、葉先が鋭く尖っていて刺さると痛いのでご注意ください。
(解説員)




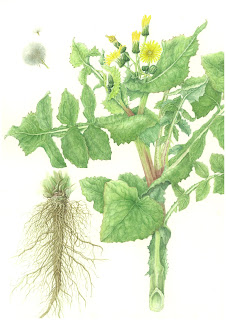
コメント
コメントを投稿